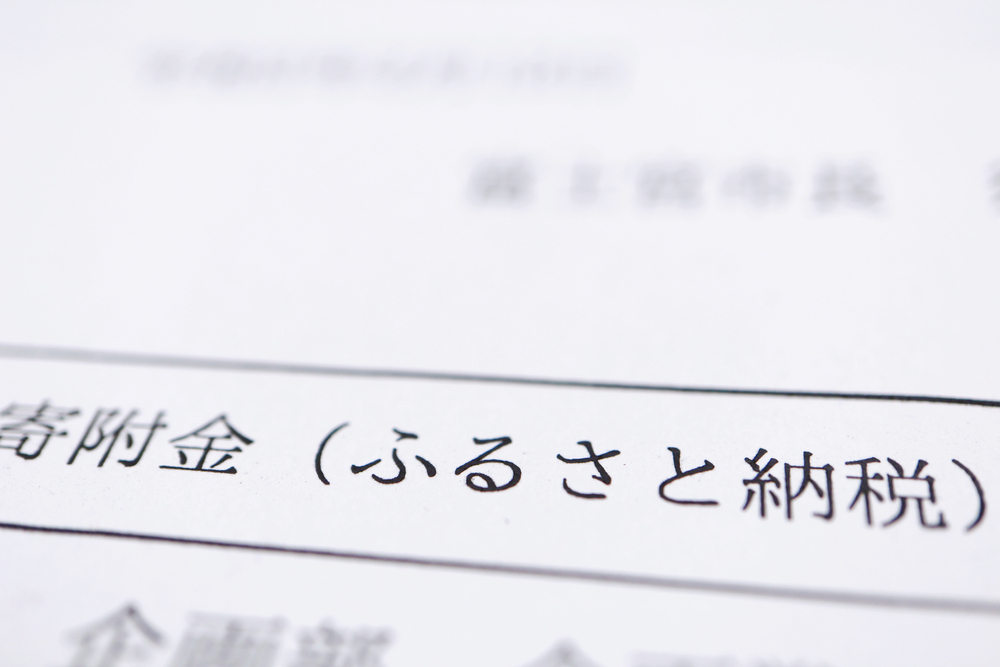目次
会社員がふるさと納税の控除を受けるには?
 会社員がふるさと納税の控除を受けるには、確定申告またはワンストップ特例制度のいずれかの手続きが必要です。それぞれの概要と手続きを受ける条件を解説します。
会社員がふるさと納税の控除を受けるには、確定申告またはワンストップ特例制度のいずれかの手続きが必要です。それぞれの概要と手続きを受ける条件を解説します。
確定申告
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得と所得税を確定し、税務署に申告する手続きのことです。 会社員の場合、勤務先が年末調整を行い、源泉徴収税の過払い分や不足分を還付・控除します。そのため、会社員にとって確定申告は不要であることが多いです。 しかし、ふるさと納税の処理は年末調整ではできないため、確定申告を行い、控除を受ける必要があります。 ふるさと納税をした会社員は、確定申告かワンストップ特例制度の活用から、どちらかを選べます。ですが、以下のいずれかのケースに該当する場合は、ワンストップ特例制度を活用できないので、確定申告を選択しましょう。 ・1年間でふるさと納税をした自治体が6以上あったとき ・年末調整できない医療費控除などの適用を受けたいとき ・2ヶ所以上から給与を受け取っている場合 ・給与以外での所得が20万円を超える場合 所得控除の種類と申告方法については、国税庁のホームページで確認できます。ワンストップ特例制度
ワンストップ特例制度は、確定申告を行わずにふるさと納税の寄附金控除が受けられる制度です。以下の条件を満たす場合に適用されます。 ・1年間でふるさと納税をした自治体が5以下 ・年末調整を受ける会社員など、確定申告の必要がない人 ワンストップ特例制度は、ふるさと納税するたびに手続きが必要になります。年間の寄附回数が少ない方におすすめです。【確定申告】会社員が控除を受けるまでの流れ
 確定申告の期間は、原則的にふるさと納税をした翌年の2月16日から3月15日です。令和3年度の確定申告については、新型コロナウイルス感染症の影響で申告が困難な場合は令和4年4月15日まで延長可能です。
会社員が、確定申告によってふるさと納税の控除を受ける場合、どのように手続きを進めていくか、確定申告の流れを簡単に説明します。
確定申告の期間は、原則的にふるさと納税をした翌年の2月16日から3月15日です。令和3年度の確定申告については、新型コロナウイルス感染症の影響で申告が困難な場合は令和4年4月15日まで延長可能です。
会社員が、確定申告によってふるさと納税の控除を受ける場合、どのように手続きを進めていくか、確定申告の流れを簡単に説明します。
1.必要なものを用意する
まずは以下の必要な書類を用意します。 ・寄附金受領証明書(寄附した自治体から送付される書類) ・源泉徴収票 ・マイナンバーカード(ない場合は、個人番号確認書類と本人確認書類の両方が必要) ・還付金を受け取る金融機関の口座番号 申告の方法などによっては提出の必要がないものもありますが、いずれも確定申告書の作成に必要ですので、漏れなく準備するようにしましょう。2.確定申告書を作成する
必要な書類を用意したら、確定申告書を作成します。確定申告書は、国税庁のホームページから申告書を印刷して手書きで作成する方法や、e-Taxで電子申告する方法、確定申告書等作成コーナーを利用して作成する方法などがあります。 その中でも、画面の指示にしたがって確定申告書を作成できる、国税庁の「確定申告書作成コーナー」を活用すると便利です。以下のサイトにアクセスし、「作成開始」ボタンをクリックして、確定申告書の作成を進めていきます。 参考:国税庁「確定申告書等作成コーナー」3.確定申告書を提出する
「確定申告書作成コーナー」で作成した確定申告書は、e-Taxで電子申告するほか、印刷して利用することも可能です。確定申告書を印刷して提出する場合は、税務署に直接持参するか郵送しましょう。 ただし、確定申告の時期は、税務署の窓口が混雑しやすくなっています。混雑回避のために、郵送やe-Tax(利用者識別番号の取得など事前準備が必要)が推奨されています。郵送などでの申告を積極的に活用すると良いでしょう。 なお、確定申告をすると、所得税の還付は確定申告の1~2ヶ月後に、住民税の控除はふるさと納税した翌年の6月~翌々年5月にかけて、毎月控除されます。【ワンストップ特例制度】会社員が控除を受けるまでの流れ
 ワンストップ特例制度を活用するためには、確定申告は必要ないものの、ふるさと納税をするたびに申請が必要です。年内に同じ自治体に繰り返し寄附した場合も同様です。具体的には、以下のような流れでワンストップ特例制度を利用します。
ワンストップ特例制度を活用するためには、確定申告は必要ないものの、ふるさと納税をするたびに申請が必要です。年内に同じ自治体に繰り返し寄附した場合も同様です。具体的には、以下のような流れでワンストップ特例制度を利用します。